一般的にお墓参りをする期間として広く知られているお彼岸ですが「具体的にどんなことをするの?」「お盆と何が違うの?」と聞かれると、うまく説明できない方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、秋のお彼岸を中心に、お彼岸の意味や由来、具体的な過ごし方、注意点、地域ごとの違いなどについてご紹介していきます。
ご供養の心を育みながら、ご先祖様に感謝を伝える時間をより豊かなものにできるよう、お役立ていただければ幸いです。。
お彼岸とは?仏教に基づく意味と由来

まずは、お彼岸の本来の意味について、仏教的な観点から詳しくご紹介いたします。
彼岸=仏教における“悟りの世界”
「彼岸(ひがん)」とは、仏教用語で「悟りの世界」を表す言葉です。対して、私たちが生きる迷いや煩悩(ぼんのう)に満ちた現世は「此岸(しがん)」と呼ばれます。
本来のお彼岸は、修行や仏教の教えを実践することによって、此岸から彼岸へと近づくことを目的とした期間でした。
しかし現代においては、「先祖を敬い、命のつながりに感謝する期間」として位置づけられ、心を清らかにし、仏教的な徳を積むことで彼岸の境地に近づくことを目指す行事として受け継がれています。
興味深いことに、このお彼岸の風習は日本独自のものであり、仏教発祥の地であるインドや中国には存在しません。
なぜ春と秋に行われるのか
お彼岸は年に2回実施されます。春は春分の日を中心とした前後3日間の計7日間、秋は秋分の日を中心とした前後3日間の計7日間です。
春分の日と秋分の日は、いずれも太陽が真東から昇り真西に沈み、昼と夜の長さがほぼ等しくなる特別な日です。
仏教において西方は「彼岸(悟りの世界)」の象徴とされているため、太陽が真西に沈むこの時期は「悟りの境地に至るのに最もふさわしい時」と考えられてきました。
また、季節の変わり目でもあるこの時期は、自然の恵みに対する感謝の気持ちや、ご先祖様とのつながりを改めて見つめ直す意味も込められているといわれています。
六波羅蜜との深いつながり
お彼岸は、仏教修行の基本である「六波羅蜜(ろくはらみつ)」を実践するという重要な教えが込められた仏教行事とされています。
六波羅蜜とは、以下の6つの修行を通じて悟りの境地(彼岸)に近づくという仏教の根本的な考え方です。
- 布施(ふせ)…人に奉仕すること(親切)
- 持戒(じかい)…規律を守ること(悪いことはしない)
- 忍辱(にんにく)…耐え忍ぶこと
- 精進(しょうじん)…たゆまぬ努力をすること(努め励む)
- 禅定(ぜんじょう)…心を落ち着かせること
- 智慧(ちえ)…真理を見抜く力を養うこと(物事を正しく見る)
お彼岸は、日常の行いを振り返り、これらの徳目を実践する絶好の機会として位置づけられています。単なる先祖供養にとどまらず、自己を見つめ直し、心の成長を図る大切な期間といえるでしょう。
お彼岸には何をするの?準備と過ごし方を解説

ここまで、お彼岸がご先祖様への感謝を通じて心を整える仏教行事であることをお伝えしてまいりました。それでは、お彼岸の期間中には具体的にどのような行いを実践すればよいのでしょうか。
この章では、お彼岸の準備から期間中の過ごし方まで、詳しくご案内いたします。
お墓参りの基本手順とマナー
お彼岸中に特に重要とされるのが「お墓参り」です。ご先祖様への感謝を表すとともに、家族が集まり命のつながりを再確認する機会でもあります。次のような流れで丁寧に行いましょう。
- お墓の掃除
雑草を取り除き、墓石を清水で丁寧に洗い清めましょう。お掃除をすることで、「清浄な場所でお迎えしたい」という気持ちを表現できます。
- お供物を供える
ご先祖様がお好きだったお菓子や果物、季節のお花などをお供えしましょう。地域によっては、春は「ぼたもち」、秋は「おはぎ」をお供えする風習もあります。
- お線香を手向ける
ろうそくに火を灯し、お線香を焚いて静かに手を合わせましょう。お線香の煙は仏様への供物であるとともに、心を落ち着かせる効果も期待できます。
- 片付けをする
お参りの後は、お供物の包装紙などのごみを必ず持ち帰り、他の方の迷惑にならないよう配慮しましょう。
- 仏壇のお手入れとお供えも大切に
ご自宅の仏壇も清め、お花やお菓子をお供えして手を合わせることも、重要な供養の一環です。お墓参りと合わせて忘れずにおこないましょう。
お寺の彼岸法要に参加する際のマナー
菩提寺で彼岸法要(彼岸会)が催される場合は、できる限り参加されることをおすすめします。読経や法話を通じて、ご先祖様への供養はもちろん、自分自身の心を見つめ直す機会にもなります。
【参加時の準備】
- 服装:地味な平服で構いません(必ずしも喪服である必要はありません)
- お布施:3,000〜10,000円程度が一般的な相場です。白い封筒に「御布施」と表書きし、住職に直接お渡しします
- 事前確認:地域や宗派によって慣習が異なる場合があるため、事前にお寺に確認しておくと安心です
2025年の秋のお彼岸はいつ?期間と各日の呼び名について

お彼岸の過ごし方や供養の具体的な方法についてご紹介しました。ここからは、実際にお彼岸がいつ行われるのか、特に2025年の秋のお彼岸の日程に注目しながら、期間中の意味や呼び名についても確認しておきましょう。
2025年(令和7年)秋のお彼岸の日程
2025年の秋のお彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間です。この1週間が「お彼岸」とされ、期間中には墓参りや仏壇へのお供えなどを行います。
具体的には次のような日程で構成されています。
- 9月20日(土)…彼岸の入り(ひがんいり)
お彼岸の始まりの日。この日から心を整え、供養の準備を始めます。
- 9月23日(火・祝)…中日(ちゅうにち)
秋分の日であり、昼と夜の長さがほぼ等しくなる特別な日です。仏教では「彼岸(悟りの世界)」と「此岸(現世)」が最も近づくとされ、最も重要な供養日といわれています。
- 9月26日(金)…彼岸明け(ひがんあけ)
お彼岸が終わる日です。仏壇やお墓にお供えしたものを下げ、お掃除をして日常生活に戻ります。
お彼岸の日程はどうやって決まる?
お彼岸の期間は、「春分の日」と「秋分の日」を中日として、その前後3日間を加えた計7日間と定められています。
春分の日・秋分の日は天体の運行により年によって1〜2日前後するため、お彼岸の期間も毎年変動します。正式な日付は国立天文台が発表する暦要項によって決定されます。
| 彼岸入り | 中日 | 彼岸開け | |
| 春の彼岸 | 春分の日の3日前の日 | 春分の日 | 春分の日の3日後の日 |
| 秋の彼岸 | 秋分の日の3日前の日 | 秋分の日 | 秋分の日の3日後の日 |
中日(春分・秋分の日)に重視される理由とは?
中日である春分の日・秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈む日です。仏教において、太陽が沈む「西方」には極楽浄土があるとされており、この日に供養を行うことで、ご先祖様への思いがより深く届くと考えられています。
また、中日以外の6日間は、前述の六波羅蜜を一日に一つずつ実践し、徳を積む期間として位置づけられています。中日は、家族や親戚が集まって法要を営んだり、精進料理を囲んで心身を整えるなど、大切なひとときを過ごす日でもあります。
お彼岸のお供え「ぼたもち」と「おはぎ」の違いとは?

前章では、お彼岸の期間と「彼岸入り」「中日」「彼岸明け」ついてについてご紹介しましたが、お彼岸に欠かせない伝統的なお供え物といえば、「ぼたもち」や「おはぎ」を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。
ここでは、お彼岸に欠かせない伝統的なお供え物とされている「ぼたもち」と「おはぎ」の違いについてご紹介します。
季節で呼び名が変わる理由|春は「ぼたもち」秋は「おはぎ」
「ぼたもち」と「おはぎ」は、もち米とあんこで作られた同じお菓子ですが、季節によって呼び方が変わるのが一般的です。
- 春のお彼岸
春に咲く花「牡丹(ぼたん)」にちなんで「ぼたもち」と呼ばれます。牡丹の花に見立て、丸く大きな形に作られることが多いです。 - 秋のお彼岸
秋に咲く花「萩(はぎ)」にちなんで「おはぎ」と呼ばれます。小ぶりで細長い萩の花に見立て、小さめに作られる傾向があります。
また、小豆の収穫時期に由来して、春は滑らかな「こしあん」を使った「ぼたもち」、秋は小豆の風味と食感を活かした「つぶあん」の「おはぎ」が好まれる傾向にあります。
小豆の赤には「魔除け」の意味も
「ぼたもち」や「おはぎ」に使用される小豆の鮮やかな赤色には、古くから邪気を払い災いを遠ざける力があると信じられてきました。
そのため、お彼岸にこれらをお供えすることは、ご先祖様への供養はもちろんのこと、家族の健康と平穏を願う意味も込められています。
また、甘いお菓子をお供えすることは、感謝や敬意を表す「おもてなしの心」の象徴でもあります。家族で手作りする過程を通じて、供養の気持ちをより深く育むきっかけとなることでしょう。
地方によって異なるお彼岸の行事

前章では、「ぼたもち」と「おはぎ」の呼び名の違いや、お供え物としての意味についてご紹介いたしました。お彼岸は全国共通の仏教行事ですが、その過ごし方や風習は地域によって実にさまざまです。
ここでは、沖縄・九州・広島・福島(会津地方)といった各地域における特色豊かなお彼岸の行事についてご紹介しましょう。
沖縄:仏壇と火の神への祈りを中心とした独自の風習
沖縄地方のお彼岸は、本土で一般的なお墓参りよりも、仏壇や「火の神(ヒヌカン)」への祈りが重視されます。
家庭の台所に祀られる火の神に対し、ウチカビ(あの世で使用するとされる紙銭)や供物を捧げ、家族の無病息災とご先祖様の加護を祈願します。
この風習は、中国や台湾などからの文化的影響を受けた独自のものであり、お彼岸を「家庭内での供養の機会」として重視している点が大きな特徴といえるでしょう。
九州:仏壇を美しく飾り、心を込めたお供えを
九州地方でのお彼岸は、仏壇に季節の果物やご先祖様がお好みだったお菓子を丁寧にお供えするのが一般的です。
また、地域によっては「彼岸団子」を手作りしてお供えする風習も大切に受け継がれています。
親戚同士や近隣の方々でお供え物を持ち寄ることも多く、仏壇周りを美しく整えて、感謝の気持ちを込めて静かに手を合わせる姿が見られます。
広島県:幻想的な「灯籠流し」でご先祖様を供養
広島県では、お彼岸の時期に「灯籠流し」を行う地域があります。灯籠に火を灯し、静かに川へ流すことでご先祖様の霊を供養するこの美しい行事は、本来はお盆の風習でしたが、地域によっては秋のお彼岸でも執り行われています。
水面に揺らめく幻想的な光の中で静寂に祈るこの行事は、自然と調和した日本独特のご先祖様供養の形といえるでしょう。
福島県(会津地方):華やかな「彼岸棚」と地域の絆を大切にする風習
福島県の会津地方では、仏壇の周囲を季節の草花やお供え物で華やかに飾り立てる風習があります。
特に「彼岸棚」と呼ばれる専用の供養棚を設ける家庭も多く、そこに新鮮な野菜や果物、手作りの団子などを美しく並べて心を込めて供養します。
また、この地方ではお彼岸の期間中に親戚や近隣の家を訪問し、それぞれの仏壇に手を合わせる「お参り回り」の文化も深く根付いており、地域のつながりの中でご先祖様への供養を大切にする温かい姿勢が感じられます。
お彼岸とお盆の違いを理解して、より深い供養を
お彼岸は、春分の日・秋分の日を中心とした7日間に行われる仏教行事であり、ご先祖様への供養とともに、自分自身の心の在り方を静かに見つめ直す期間とされています。
一方、お盆は毎年7月または8月(地域により異なる)に行われ、ご先祖様の霊が一時的に現世へ帰ってこられるとされる特別な時期です。
迎え火・送り火や盆踊りなどの伝統的な風習があり、家族総出でご先祖様の霊をお迎えし、丁寧におもてなしして供養するのが大きな特徴です。
つまり、お彼岸は「供養の心をご先祖様にお届けする期間」、お盆は「ご先祖様の霊をお迎えしておもてなしする期間」という違いがあります。
これらの意味や風習の違いを正しく理解することで、より丁寧で心のこもったご供養の実践につながるでしょう。
お彼岸に関するよくある質問
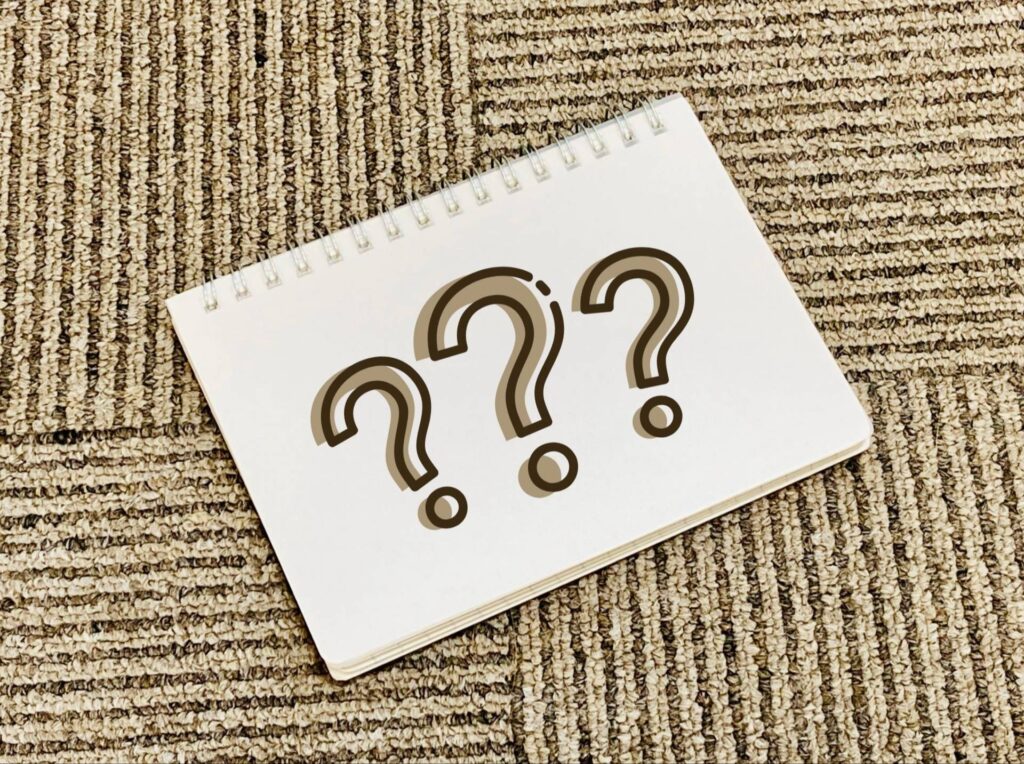
ここからは、お彼岸を迎えるにあたってよくある質問について、Q&A形式でご紹介していきます。
Q1.お彼岸に僧侶に渡すお布施の相場は?
菩提寺で行われる彼岸法要(彼岸会)に参加する場合に用意するお布施は、5,000円〜10,000円程度が目安と言われています。
しかし、お布施の金額に明確な決まりはなく、地域や寺院の慣習によって異なるため事前に確認すると安心です。表書きは「御布施」とし、白無地または蓮の花が描かれた封筒を使用しましょう。
Q2.お彼岸にはどんなお花をお供えしたら良いの?
仏壇やお墓には、香りが強すぎず、長持ちする花が適していると言われています。このため、お彼岸には、菊やリンドウ、カーネーション、キンセンカなどがよく選ばれていますが、ご先祖様が好きだった花を選ぶのも良いでしょう。
ただし、トゲのあるバラなどは避けるのがマナーです。
Q3.お彼岸のお供え物のお返しはどうすればいいの?
お彼岸のお供え物に対するお返しは、基本的には不要とされています。どうしてもお礼の気持ちを伝えたい場合は、後日「志(こころざし)」などの表書きで簡単な品を贈ると良いでしょう。
高額な返礼はかえって相手に気を遣わせてしまうため注意しましょう。
Q4.初彼岸には何をするの?
故人様が亡くなって初めて迎えるお彼岸は「初彼岸(はつひがん)」と呼ばれています。規模に決まりはなく僧侶を招いて法要を営むこともあるようですが、お墓参りや仏壇へのお供えを丁寧に行い、心を込めて供養することが大切です。
おわりに

お彼岸とは、春分の日・秋分の日を中心とした7日間に、ご先祖様への感謝の気持ちを込めてお伝えする大切な仏教行事です。
お墓参りや仏壇のお手入れ、精進料理を通じた心身の浄化などを実践することで、日頃の慌ただしい生活から離れ、静寂の中で心を整える貴重な時間を過ごすことができます。
また、春の「ぼたもち」、秋の「おはぎ」といった季節ごとのお供え物には、それぞれ深い意味が込められており、日本文化の豊かな精神性や、長い歴史の中で培われてきた信仰心の深さを感じ取ることができます。
お彼岸には厳格な決まりごとが多数あるわけではありませんが、ご先祖様を敬う気持ちと、心を込めてご供養を行うことが何より重要です。
形式的な作法にとらわれすぎることなく、自分自身や家族の心が穏やかに満たされるような時間を過ごすことこそが、現代社会におけるお彼岸の本質的な意味といえるでしょう。
この記事が、皆様にとってより心豊かなお彼岸をお過ごしいただくための一助となれば幸いです。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
