少し前までは「お墓は代々継承されるもの」という考えが一般的でした。しかし近年では、「遠方でお参りが困難」「後継者がいない」「子どもへの負担を軽減したい」といった理由から、先祖代々のお墓を撤去し、新たな供養方法へと移行する「墓じまい」を選択される方が増加しています。
そこで今回は、墓じまいとは何か、また墓じまいを実施する場合の具体的な進め方や費用、そして墓じまい後の供養の選択肢まで、まとめてご紹介いたします。
墓じまいをご検討中の方にとって、有益な情報となれば幸いです。
墓じまいとは何か?選ばれる理由と背景

まず、墓じまいの基本的な概念と、現代社会において選ばれる理由について詳しくみていきましょう。
墓じまいとは
墓じまいとは、現在あるお墓を解体・撤去し、更地に戻した上で墓所の管理者にその使用権を返還することを指す言葉です。墓じまいを行う場合は、納められているご遺骨を取り出して供養し、新たな供養先へ移す「改葬」という手続きも必要となります。
改葬をおこなう場合、墓地・霊園が所在する地域の市町村長、または特別区の区長の許可が必要となります。
墓じまいが選ばれる社会的背景
現代社会における墓じまいの増加には、以下のような構造的な変化が影響しています。
- 社会構造の変化
- 少子高齢化の進行
- 核家族化の浸透
- 都市部への人口集中
- 価値観の多様化
- お墓に対する従来の固定観念からの脱却
- 供養方法の選択肢拡大への関心
- 現実的な課題
- 無縁墓化への懸念
- 維持管理の負担軽減ニーズ
具体的には、都市部で生活する子世代が故郷に戻らないケースが増加し、結果として墓地の維持継承が困難になる状況が頻発しています。
子世代の立場からも、遠方にある墓地の管理は経済的・時間的負担が大きく、現実的な課題となっているのが実情です。
このような背景から、「墓石による供養が絶対的に必要」という従来の価値観にとらわれることなく、納骨堂や樹木葬、散骨といった現代的な供養スタイルを積極的に選択する方が増えています。
また、後継者不在により無縁墓となってしまうリスクを回避するため、墓地が荒廃する前に自らの意思で墓じまいを実行したいと考える方も少なくありません。
これは、先祖への敬意を保ちながら現実的な解決策を模索する、現代らしい選択といえるでしょう。
墓じまいのメリットとデメリット

墓じまいが選ばれる社会的背景をご紹介いたしましたが、実際に墓じまいを検討する際には、その利点と注意すべき点を十分に理解しておくことが重要です。
ここでは、墓じまいのメリットとデメリットを整理してご紹介いたします。
墓じまいのメリット
- 維持管理からの解放:年間管理費や清掃作業などの継続的な負担から解放されます
- 継承問題の解決:後継者がいない場合でも、安心して先祖の供養を続けることができます
- 供養スタイルの自由度向上:納骨堂、樹木葬、手元供養など、ライフスタイルに合わせた多様な供養方法を選択できます
- 経済的・時間的負担の軽減:遠方への墓参りにかかる交通費や時間的コストを大幅に削減できます
墓じまいのデメリット・注意点
- 親族間の合意形成の困難さ:親族全員の同意が得られない場合、深刻な家族間トラブルに発展する可能性があります
- 予期せぬ費用の発生:僧侶へのお布施に加え、離檀料など当初想定していない費用が必要となる場合があります
- 新しい供養方法への適応不安:従来とは異なる供養スタイルに対して、心理的な違和感や不安を感じる可能性があります
- 精神的な後悔のリスク:長年慣れ親しんだ墓所や、思い出深い場所を手放すことに対する喪失感を抱く場合があります
墓じまいの進め方|7つのステップで理解する手続きの流れ

墓じまいのメリットとデメリットをご理解いただいたうえで、実際に墓じまいを進める場合の具体的な手順をご説明いたします。
適切な順序で進めることで、トラブルを回避し、円滑な墓じまいを実現しやすくなります。
1. 親族への相談と合意形成
墓じまいを成功させる最も重要な要素は、家族・親族間での十分な合意形成です。事後報告による親族間トラブルを避けるため、墓じまいの必要性や理由を丁寧に説明し、全員の理解と同意を得ることから始めましょう。
2. 墓地管理者との協議
墓地のある寺院や霊園の管理者に墓じまいの意向を伝え、協議を行います。撤去作業の方法、必要書類の準備、手続きの流れなど、具体的な要件を詳しく確認しておくことが重要です。
3. 改葬先の選定と決定
ご遺骨の新たな納骨先を決定します。一般墓、永代供養墓、納骨堂、樹木葬、散骨、手元供養など、多様な選択肢の中から、費用面や宗教的条件、立地条件などを総合的に考慮して最適な改葬先を選びましょう。
4. 改葬許可証の取得
現在の墓地がある自治体の役所において改葬許可申請を行い、改葬許可証を取得します。申請には「改葬許可申請書」のほか、「埋葬証明書(納骨証明書)」「改葬先の受入証明書」などの書類が必要となります。
5. 閉眼供養を行う
僧侶に依頼し、墓石からご先祖様の魂をお送りする「閉眼供養」(魂抜き)の法要を営みます。これにより、墓石は宗教的な意味を持たない単なる石材となります。
6. 墓石の解体・撤去
石材店などの専門業者に委託し、墓石の解体・撤去とご遺骨の取り出しを行います。作業完了後は墓所を更地の状態に復旧し、管理者に使用権を返還します。
この際、管理者から返還に関する書類の提出を求められる場合があります。
7. 新たな納骨先で納骨・供養
新たに決定した納骨先にご遺骨を納骨し、必要に応じて開眼供養(魂入れ)を実施します。これをもって墓じまいの一連の手続きが完了となります。
墓じまいにかかる費用と内訳

墓じまいを検討する際、多くの方が抱かれる不安の一つが費用面の問題です。ここでは、墓じまいに必要な費用項目とその相場について詳しくご説明いたします。
なお、以下の費用は墓地の立地条件、墓所の規模、供養内容などによって大きく変動するため、あくまで参考目安としてご活用ください。
| 項目 | 費用相場 | 内容 |
| 解体・撤去費用 | 10〜20万円程度(1㎡あたり) | 墓石の解体・撤去・整地 |
| 改葬許可手数料 | 数百円〜1,500円 | 自治体の手続き費用 |
| 閉眼供養 | 3〜5万円 | 僧侶へのお布施 |
| 離檀料 | 0〜20万円 | 寺院を離れる際のお礼(寺院墓地の場合) |
| 納骨・開眼供養 | 5〜30万円 | 新しい納骨先での供養 |
| 新たな納骨先費用 | 数万円〜300万円 | 納骨堂・永代供養墓・樹木葬などの費用 |
墓じまい後の供養の選択肢
墓じまいの手続きと費用についてご理解いただいたところで、最も重要な要素である「ご遺骨をどのように供養するか」について詳しくご説明いたします。
それぞれの供養方法には固有のメリットとデメリットがありますので、ご家族の状況に最適な選択肢を見つけていただければと思います。
| 供養方法 | メリット | デメリット |
| 一般墓への改葬 | 従来の墓石による供養スタイルを維持できるため、親族からの理解を得やすく、慣れ親しんだ供養方法を継続できます。 | 新たな墓地取得費用や継続的な管理費が発生し、将来的には再び継承者の問題に直面する可能性があります。 |
| 納骨堂・屋内墓苑 | 都市部の便利な立地に設置されることが多く、天候に左右されずにお参りできます。管理も行き届いており清潔な環境が保たれます。 | 契約期間に制限がある場合、期間満了後は合祀墓への移葬となることもあるため注意が必要です。 |
| 永代供養墓 | 一括払いで将来の管理費が不要となり、継承者がいなくても寺院や霊園が永続的に供養を行ってくれます。 | 多くの場合、最終的には他のご遺骨と一緒に合祀されるため、個別の供養ができなくなります。 |
| 樹木葬 | 自然豊かな環境での供養が可能で、墓石が不要なため費用を抑えることができます。環境に配慮した供養方法として注目されています。 | 埋葬区画に制限があり、希望する時期に利用できない場合があります。また、自然災害による影響を受ける可能性があります。 |
| 散骨 | 海や山などの自然環境に散骨することで開放的な供養が実現でき、費用も比較的抑えることができます。 | ご遺骨が物理的に残らないため、お参りする場所がなくなることに不安を感じる方もいらっしゃいます。 |
| 手元供養 | ご遺骨の一部を自宅で保管することで、故人をより身近に感じながら供養を続けることができます。 | 相続時や引っ越し時の取り扱いが複雑になる場合があり、将来的な管理について事前に検討が必要です。 |
墓じまいに関してよくあるトラブルと対策
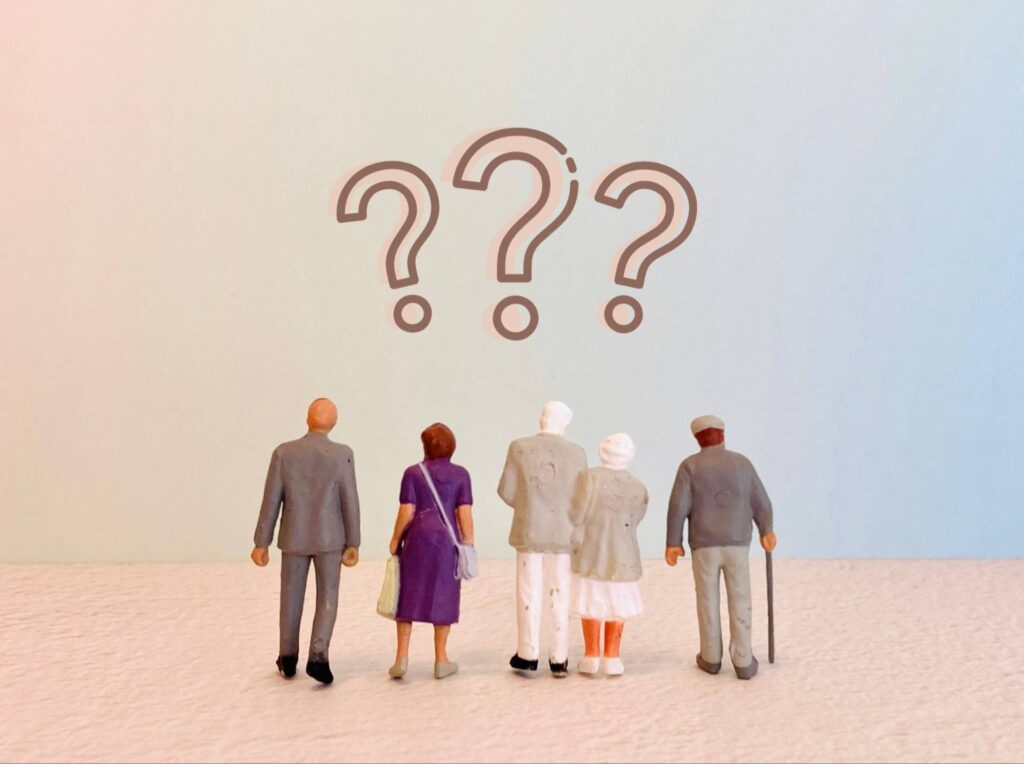
墓じまいは人生の中でも重要な判断です。しかし、進め方によっては思わぬトラブルに発展することもあります。ここでは、実際によくあるトラブルとその対処法についてご紹介します。
1.親族と意見が合わない?
「勝手に墓じまいを決められた」「先祖代々の墓を守るべきだ」といった親族間での価値観の相違が、深刻な家族問題に発展するケースです。
特に、日常的な墓地管理に関わっていない親族との間で対立が生じやすい傾向があります。
《対策案》
早い段階で親族全員に相談し、情報を共有することが何よりも大切です。将来的な管理の難しさや維持費の負担を考慮し、墓じまいという大きな決断に至った背景を丁寧に伝え、できる限り納得を得られるよう努めましょう。
必要に応じて、親族が一堂に会して石材店や寺院の担当者から直接説明を受ける機会を設けることも効果的です。第三者からの客観的な説明により、親族の理解が深まる場合があります。
2.寺院や霊園とのトラブル(離檀料など)
寺院が墓じまいに対して消極的な姿勢を示したり、離檀料として予想以上の高額費用を請求されたりするトラブルです。
時には「ご先祖様を粗末に扱っていいのか」といった感情的な対立に発展することもあります。
《対策案》
まず、長年にわたってご先祖様の供養をしていただいた感謝の気持ちを誠実に伝えることから始めましょう。その上で、墓じまいを決断せざるを得ない現実的な事情を冷静に説明し、理解を求めることが大切です。
離檀料については法的な基準が存在しないため、提示された金額が適正かどうかを他の寺院や石材店、行政書士などに相談して判断することをおすすめします。
話し合いが難航する場合は、宗教法人や法律の専門家に仲介を依頼することも有効な解決策の1つです。
3.遺骨の行き先が決まっていない
墓じまいの手続きを進めてしまったものの、ご遺骨の新しい納骨先が決まっていないため、改葬許可申請ができずに手続きが停滞してしまうケースです。
《対策案》
墓じまいの計画段階で、必ず改葬先を確定させてから手続きを開始しましょう。改葬許可申請には改葬先からの受入証明書が必要となるため、納骨先が決まっていなければ申請自体ができません。
永代供養墓、納骨堂、樹木葬、手元供養など、多様な選択肢の中から家族の状況に最適な供養方法を選ぶため、事前に複数の施設を見学し、費用や条件を比較検討することが重要です。
地域の宗教的背景や宗派の制約も考慮に入れて、慎重に選択しましょう。
おわりに~円滑な墓じまいの実現に向けて~

墓じまいは、現在のお墓を撤去し、ご先祖様の供養を新たな方法に移行させる人生における重要な決断です。少子高齢化や核家族化の進展により、後継者不在や維持管理負担の軽減を目的として、この選択をされる方が年々増加している現実があります。
しかしながら、適切な手順を踏まずに進めてしまうと、親族間での深刻な対立、寺院や霊園との関係悪化、改葬先の準備不足といった深刻な問題に発展する可能性があります。
このようなトラブルを回避するためには、計画段階から関係する全ての親族との丁寧な合意形成を図り、改葬先の選定や必要費用を事前に明確化しておくことが不可欠です。
現代では納骨堂、永代供養墓、樹木葬、散骨、手元供養など、従来の墓石による供養以外にも多様な選択肢が用意されています。
これらの特徴とメリット・デメリットを十分に比較検討し、ご家族の価値観やライフスタイルに最も適した方法を選択することで、後悔のない形でご先祖様への敬意を示すことができるでしょう。
墓じまいは専門的な知識と複雑な手続きを伴う作業であるため、不明な点や不安がある場合は、石材店、行政書士、寺院などの信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
適切な専門家の助言を得ることで、安心して手続きを進めることができ、円滑な墓じまいの実現につながります。
大切なご先祖様への供養の形は変わっても、敬う気持ちに変わりはありません。現代の生活様式に適した供養方法を選択することで、将来にわたって安心してご先祖様をお守りできる環境を整えていただければと存じます。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
