湯灌(ゆかん)とは、故人様の体を清め、来世への旅立ちに備える葬儀の儀式のひとつです。単に体を洗浄するというものではなく、宗教的な意味やご遺族の心を癒す役割も持ちます。
湯灌では、時間の経過とともに現れてくる体の変化へのケアも行うなど、故人様の尊厳を守りながら旅立ちの準備を整えます。
この記事では、湯灌の意味や流れ、代表的な「古式湯灌」と「洗体湯灌」の違い、費用やマナーまで詳しく解説しています。
湯灌(ゆかん)とは?意味と役割

湯灌とは、故人様の体をお湯で清めるという儀式のことで、人生最後の入浴とも言えます。日本では古くから、清らかな状態で来世へ旅立つための大切な習わしとされてきました。
湯灌には、大きく分けて次のような意味や役割があります。
宗教的な意味
仏教や神道では、亡くなった方を清らかな姿で送り出すことが、幸せな来世を願ううえで欠かせない行いとされています。古来より「水は穢れを祓う」と考えられ、神社での手水や禊(みそぎ)と同様に、湯灌にも浄化の意味が込められてきました。
とりわけ古式湯灌では、白布をかけた桶や柄杓を用い、静かに体を清めていきます。これは単なる洗浄ではなく、「この世での汚れや苦しみをすべて流し、新たな世界へと導く」という象徴的な行為だと言われています。
故人を労い、ご遺族様の心を癒す
湯灌は、長い人生を歩み、家族や友人のために尽くしてくれた故人様に、感謝の気持ち「ありがとう」を伝えられる貴重な時間だといえます。
例えば、髪を梳(と)きながら「いつも笑顔だったね」と声をかけたり、肌を清めながら手を握ったりすることは、ご遺族にとって心の整理を促す時間となど、グリーフケアのひとつとも言えます。
衛生的な理由
亡くなった後の体は時間の経過とともに変化し、皮膚の乾燥や変色、匂いなどが現れてきます。特に、夏場など気温の変化が激しい季節は、防腐処置や医療的ケアが必要になることもあるでしょう。
湯灌では、髪や皮膚を丁寧に洗浄し、爪を切り、口元や顔まわりを整え、故人様の尊厳を保ちます。さらに、納棺後の外見を美しく保つことで、葬儀の際にお別れに訪れる方々にも安心して最後のご対面をしていただけることでしょう。
湯灌の種類:古式湯灌と洗体湯灌

湯灌は、宗教的な意味合いや衛生的な理由で行うものだとご紹介しました。そんな湯灌には、大きく分けて2つの種類があります。
- 古式湯灌(こしきゆかん)
- 洗体湯灌(せんたいゆかん)
この2種類のほかに、清拭(せいしき)で済ませるという方法もあります。
ここでは、「古式湯灌」と「洗体湯灌」について、それぞれの特徴をご紹介します。
古式湯灌
古式湯灌は、桶やかけ湯で体を清めるという伝統的な方法です。アルコール綿や白布、白装束を用い、念仏や読経を伴うこともあります。宗教色が強く、地域や宗派によって細かな作法が異なるケースもあります。
特徴は、伝統的で荘厳な雰囲気の中で、儀礼性や精神性を大切にできることです。費用は3〜6万円程度が相場だと言われています。
洗体湯灌
洗体湯灌は、湯船やシャワーを使って個人様を丁寧に洗い清めるというもので、葬儀社や湯灌師など専門のスタッフによって行われることが一般的です。無宗教の葬儀の場合でも行いやすく、ご自宅で移動式の湯船など専用の機材を持ち込んで行うことも可能です。
特徴は、医療的な衛生管理も重視したうえで、必要に応じて体液の処置や防腐措置を行うなど、体の変化を最小限に抑えられる点です。費用は、6〜10万円程度が相場だと言われています。
現在は、こちらの洗体湯灌が一般的となっています。
湯灌の流れ

湯灌には、宗教色の強い伝統的な「古式湯灌」と、衛生面に優れ体の変化を最小限に抑えられる現代的な「洗体湯灌」の2つがあることをご紹介しましたが、どちらも納棺前に行われます。
なお、湯灌は、厳密に言えば故人様の体を洗浄して来世への旅立ちに備えるというものですが、実際は、その後で行う死化粧や死装束(旅支度)の着付けも含めた一連の流れとして行われることが一般的です。ここからはその流れをご紹介します。
末期の水を取る
湯灌の前に「末期の水(まつごのみず)」を取ります。ガーゼや筆で故人様の唇を湿らせる儀式で、故人への最後の愛情表現として行われる大切な習わしです。「息を吹き返してほしい」という願いや「あの世で喉が渇くことなく安らかに過ごしてほしい」といった祈り、そして生前への感謝や労いの気持ちなどが込められた儀式とされています。
由来については、お釈迦様の入滅時に清浄な水を捧げたという仏教の故事をはじめ、さまざまな説が語り継がれています。
洗髪・洗体
末期の水を撮った後、髪を洗い、顔や体をお湯で清めます。洗体湯灌ではシャワーや浴槽を使用し、古式湯灌では桶でかけ湯を行います。これらの行為が、厳密にいえば湯灌にあたります。
死化粧
お湯でのお清めが終わったら、自然な表情や肌色になるように化粧を施します。男性の場合は髭を剃り、女性の場合は口紅や頬紅を軽く差し、髪を整えて生前に近い安らかな姿にします。
死装束(旅支度)の着付け
死化粧に続いて、故人に死装束を着せます。これは来世への旅の衣装とされ、仏衣、手甲、脚絆、六文銭、頭陀袋、天冠などを身につけます。六文銭は三途の川の渡し賃、頭陀袋は旅の道具袋という意味があると言われています。
納棺
死装束の着付けが整ったら、故人様をお棺に納めます。この時、故人様の愛用品や思い出の品をお棺に入れます。なお、火葬の際に燃えないものは入れられないため、気になる場合は事前に葬儀社に確認しましょう。
湯灌に関するよくある質問
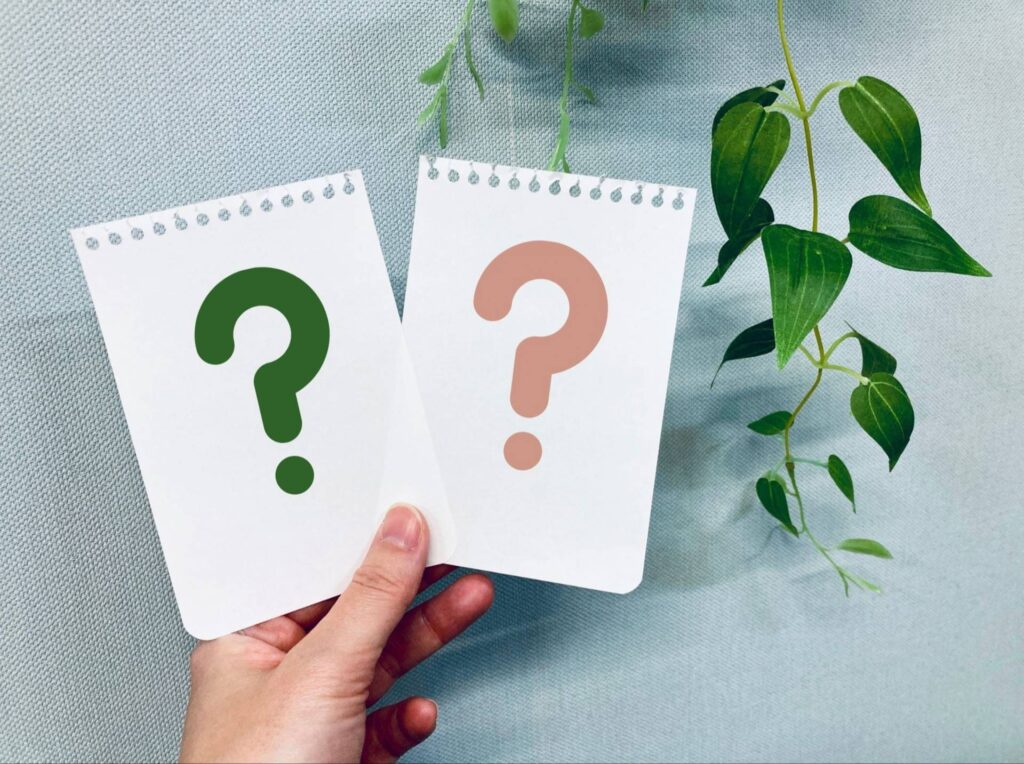
ここからは、湯灌を行う際によくある質問について、Q&A形式でご紹介していきます。
Q1.湯灌には立ち会った方がいいですか?
立ち会いは必須ではありませんが、この時間に声をかけたり手を握ったりすることで、心残りや後悔が少なくなり、悲しみを受け入れる助けにもなることでしょう。宗教的には、水で清める行為は、「穢れを祓い、魂を新たな世界へ導く」と言われています。
しかし、ご遺体を見るのが辛いと感じる方もいることでしょう。湯灌に要する時間は、1時間半〜2時間程度が目安のため、時間も考慮しながらご自身で立ち会うかどうか、判断することをおすすめします。
Q2.湯灌に立ち会うときの服装はどうすればいいですか?
湯灌に立ち会うときは、派手な柄・明るい色の服装は儀式の雰囲気を損ねる可能性があるため控えるのがマナーです。このため、喪服が望ましいと言えますが、黒・紺・グレーなど落ち着いた色味の平服でも問題はないでしょう。
Q3.病院で「エンゼルケア」を受けた場合でも湯灌は必要ですか?
エンゼルケアを受けていたとしても、湯灌を行うことには十分な意味があります。
エンゼルケアはあくまで病院での死後処置で、体を拭いたり顔や髪を簡単に整えたり、医療器具を外すなどの基本的な対応にとどまります。
一方で湯灌は、全身の洗浄や洗髪に加え、爪切りや髭剃り、死化粧、死装束の着付けまでを含む、より丁寧な儀式です。宗教的・象徴的な意味合いもあり、故人を新たな旅路へ送り出す「旅支度」としての役割を果たします。
そのため、衛生面を整えるだけでなく、ご遺族が最後に感謝や想いを伝え、心の整理をする大切な時間にもなります。エンゼルケアで基本の処置が済んでいても、湯灌を選ばれるご家庭が多いのはそのためだと言えるでしょう。
おわりに

湯灌は、宗教的な意味と衛生面でのケアを兼ね備えた、大切な送りの儀式です。故人様の尊厳を守り、穏やかな表情で来世へ旅立てるよう支える役割を果たしています。
湯灌には「古式湯灌」と「洗体湯灌」という2つの形があります。どちらも故人様に感謝の気持ちを伝え、心を込めて美しく旅支度を整えるためのものですが、現在は洗体湯灌が主流となっています。
湯灌を単なる儀式と捉えるのではなく、その背景や流れを理解することで、「故人様と向き合い、敬いと感謝を伝える貴重な機会」にできます。さらに、ご遺族にとっても心を整理し、故人様を送り出す心の準備ができる時間となるでしょう。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
