ご家族や親しい方が「危篤(きとく)だ」と伝えられたとき、戸惑いや不安で何をすべきかわからなくなる方がほとんどだと思います。
そこで今回は、「危篤とはどういう状態なのか?」という基本から、症状の特徴、連絡すべき相手、具体的な対応方法、そして万が一の場合の流れまでをまとめてご紹介します。
冷静な判断が求められる場面でもあり、慌てずに行動できるよう、参考にしてください。
危篤とは?意味と状態を知っておこう

医師から「危篤です」と告げられると、家族や親族は非常に深い衝撃を受けるものですが、「危篤」とはどのような状態をさすのでしょうか。医療現場での判断基準など、正確な意味を押さえておくと、動揺を抑え、適切に対応する助けになります。
以下で詳しく「危篤」の意味と、「重篤」との違いを併せて解説していきます。
医療現場での「危篤」とは
「危篤」とは、医学的に生命の危険が差し迫った状態を指し、「治療を継続しても回復の可能性が極めて低い」と医師が判断した状態のことです。
多くの場合、医師から「ご家族をお呼びください」という連絡が入るタイミングがこの危篤状態に該当します。この段階では、ご家族にとって故人様との最期の時間を過ごすことが最も重要といえるでしょう。
「危篤」と「重篤」の違い
危篤と混同されがちな言葉として「重篤(じゅうとく)」があげられます。しかし、両者の意味には大きな違いがあります。
重篤:深刻な病状ではあるものの、適切な処置をすれば回復の見込みがあり、集中治療や手術などで症状が改善する可能性がある状態です。
危篤:死期が迫っている状態で、回復は極めて難しく、生命の維持が困難な状態です。ご家族への連絡や臨終に備える段階ともいえます。
重篤から危篤へ進行してしまうケースも多く、医療現場では状態に応じて段階的に判断されます。医師の説明をよく聞くとともに、適切な行動を取ることが大切です。
危篤状態の主な症状とは
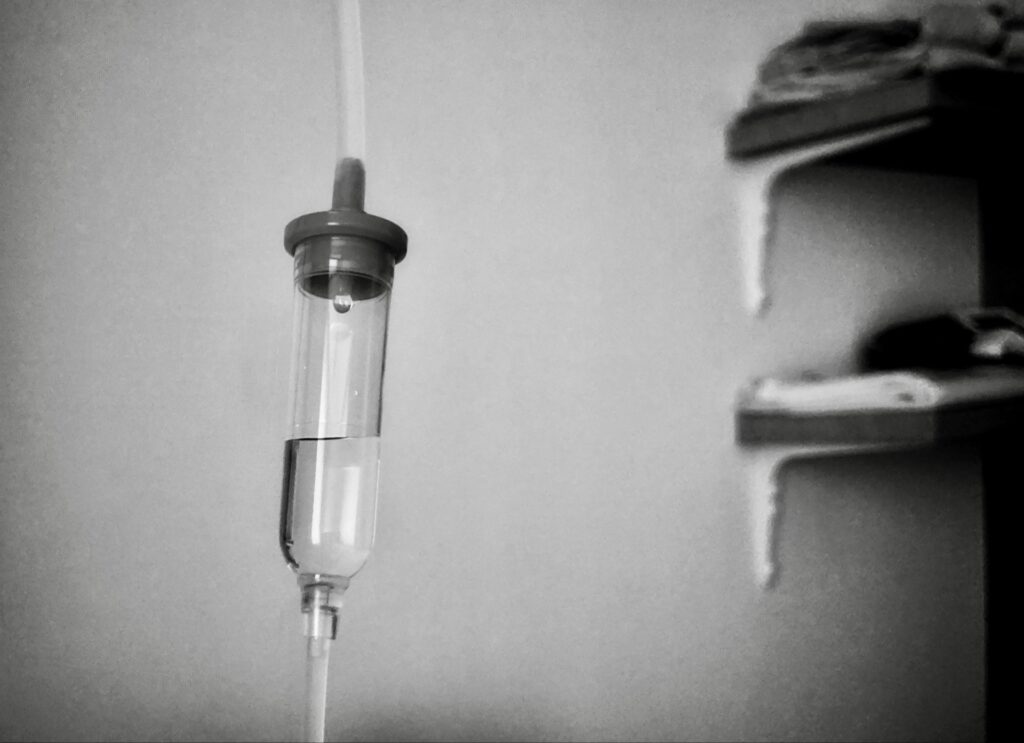
危篤の状態では、次のような症状を引き起こすことが多いです。
- 意識の低下、応答がない(昏睡)
- 呼吸が浅くなる、あるいは不規則になる
- 脈拍が弱くなり、血圧が低下する
- 手足が冷たくなり、皮膚に紫色の変化が見られる
- 尿の量が極端に少なくなる
これらの症状は、身体機能が徐々に停止しつつあるサインだと言われています。
家族が危篤と知らされたときの対応
ここまで危篤とは、どのような状態を指すのかをご紹介しました。続いては、医師から「危篤です」と告げられたときに、ご家族がとる対応についてご紹介していきます。
まずは気持ちを落ち着かせる
突然の連絡に動揺してしまうのは当然のことですが、できる限り冷静に行動したいものです。ご本人との時間を穏やかに過ごすためにも、まずは深呼吸をするなど心の準備を整えましょう。
不安や焦りの中で行動すると、大切な連絡や持ち物を忘れてしまうこともあります。メモをとる、誰か信頼できる人に相談するなど、ひとりで抱え込まず、気持ちを整理しながら対応することを意識しましょう。
病院に向かう準備をする
危篤の連絡を受けたら、次のようなものを準備して病院に向かいましょう。
- 本人の保険証や診察券
- 自分の身分証明書
- 携帯電話・充電器
- 着替えやお金(長時間の滞在を想定)
- 常用薬(自分の分)
- 筆記用具やメモ帳
なお、夜間の場合は宿泊も想定し、洗面用具やタオル類を持っていくと安心です。また遠方の場合は、交通手段の確認を忘れないようにしましょう。
自宅で危篤状態になってしまった場合は?
自宅で危篤と思われる状態になった場合は、すぐにかかりつけ医や訪問看護師に連絡を入れ、医師の指示に従って対応しましょう。かかりつけ医がいない場合や、連絡がつかない場合には迷わず救急車を呼んでください。
事前に在宅医療を受けている場合は、対応マニュアルが用意されていることもあるため、確認しておくと良いでしょう。また、周囲の家族とも役割を分担するなど、ひとりで抱え込まずに対応することが大切です。
危篤の連絡は誰にどう伝える?

危篤と告げられた場合、冷静にはいられない状況ではありますが、ご家族やご親族様にも今の状況を伝えておくことが望ましいです。どの範囲までに知らせるのか、どのように知らせるかは、ご本人様の状態によっても異なるため、あくまでも一例としてご紹介していきます。
危篤の連絡する範囲の目安
基本的に本人様から見て三親等以内の親族には連絡を入れるようにしましょう。
【三親等以内の親族】
配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹・祖父母、孫、おじ、おば、いとこ など
また、本人が会いたがっていた友人や知人がいれば、その方にも知らせるのが望ましいでしょう。最期に立ち会う機会を大切にすることが、ご遺族様や関係者にとっての心の整理にもつながります。連絡するか迷った場合は、「後悔しないか」を基準に考えるとよいでしょう。
危篤を連絡する手段とマナー
危篤を伝える連絡方法として考えられるものは、以下になります。
- 電話
- メールやSNS
- 電報
電話:もっとも迅速で確実です。早朝や深夜でも失礼にはあたりません。
メール・SNS:連絡がつかない場合や、緊急性が低い連絡先に適しています。利用する際は、相手の生活リズムや年齢層に配慮しましょう。
電報:遠方の親族や高齢者に、フォーマルな手段として利用されることがあります。
伝える内容は、「誰が危篤なのか」「現在の状況」「来てもらいたいかどうか」を簡潔にまとめましょう。
相手の感情にも配慮しつつ、事実を丁寧に伝えることが大切です。連絡を受けた側も動揺してしまう可能性があるため、冷静に落ち着いて話すように心がけましょう。
危篤の方にかける言葉や接し方
本人に意識がある場合、優しく声をかけたり、手を握ったりすることが大きな安心感となります。
言葉は難しく考える必要はありません。「ありがとう」「来たよ」「大丈夫だよ」といった、ご本人に安心を与える一言を大切にしましょう。無理に話しかけ続ける必要はなく、そばにいるだけでも充分です。
もし意識がない場合でも、聴覚は最後まで残っていると言われています。やさしい声で語りかけることで、安心を届けることができるでしょう。また、ご本人の好きだった音楽を流すことも有効です。
危篤から亡くなった場合の対応

ご家族の願いも虚しく、最期の時を迎えられた場合には、必要な手続きを進めることが求められます。ご遺体の搬送や葬儀の手配など慌ただしい対応が続くため、あらかじめ流れを知っておくと安心です。
医師による死亡確認
病院で亡くなった場合は、医師が死亡を確認し、「死亡診断書」を発行します。この書類は火葬許可証の取得に必要です。
一方、自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医に連絡を入れましょう。かかりつけ医が訪問できない、もしくは突然死と見なされる場合には、警察に連絡し、検視を受ける必要が生じることもあります。
退院・搬送の手続き
死亡が確認されたら、すみやかに葬儀社へ連絡して遺体の搬送を依頼しましょう。また、病院の看護師や地域の相談窓口から紹介してもらえることもあります。あらかじめ葬儀社を決めていない場合は、相談してみましょう。
いずれの場合も、病院では長時間の遺体安置ができないため、搬送先(自宅または安置施設)をあらかじめ決めておくことが大切です。
自宅で亡くなった場合の注意点
自宅で亡くなった場合で医師による死亡の診断が受けられない場合は、警察に連絡する必要があります。異状死の可能性があると判断されると、現場確認や事情聴取が行われることもあります。ただし、すぐに事件性がないと判断されれば、火葬許可の手続きに必要な「死体検案書」が発行されるのでご安心ください。
葬儀の準備と進め方
信頼できる葬儀社に連絡し、葬儀の日程や費用、形式について相談します。準備期間が短いため、できれば事前に見積もりを取り、次のことについて家族で話し合っておくと良いでしょう。
- 宗教・宗派
- 通夜・葬儀の日程
- 会場・参列者数
- 連絡すべき相手
なお、菩提寺がある場合は、通夜・葬儀の日程に関して僧侶との事前調整が必須となります。
危篤に対してよくある質問
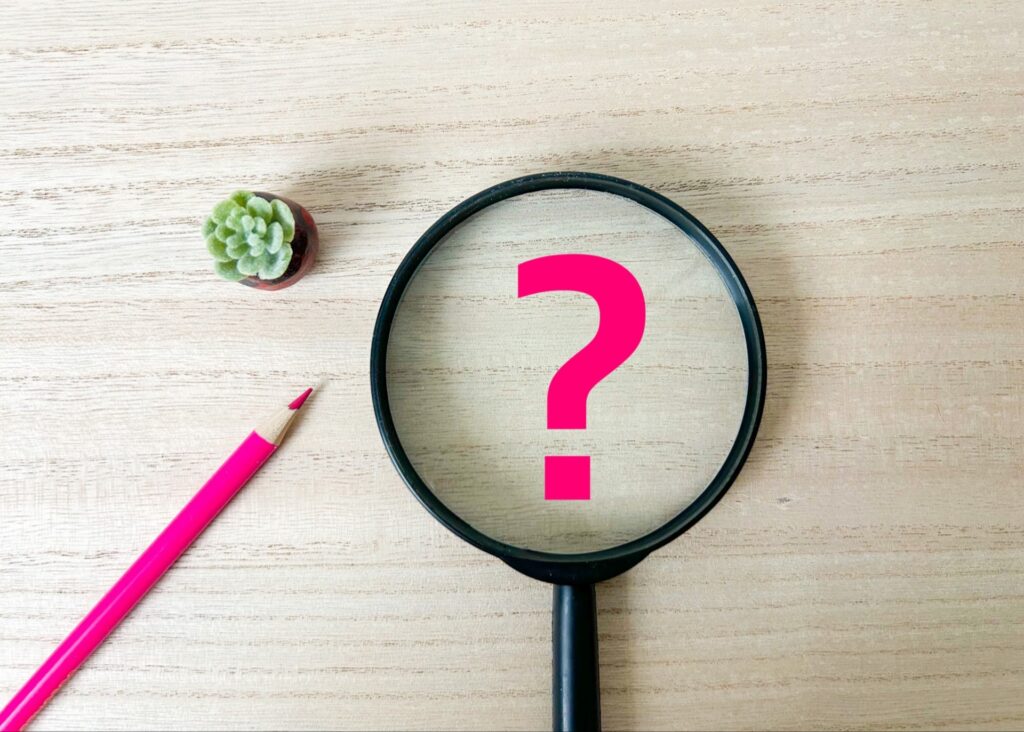
ここからは、危篤の状態にあたってよくある質問について、Q&A形式でご紹介していきます。
Q1.危篤の連絡を受けたが、誰に連絡すればいいかわかりません
危篤の連絡を受けたときは、まず三親等以内の親族(両親・子ども・兄弟姉妹・祖父母・おじ・おば・いとこなど)に連絡するのが一般的です。
また、本人が会いたがっていた方や、特別に親しかった友人・知人がいれば、その方にも連絡すると良いでしょう。
すぐに判断が難しい場合は、家族や他の親族と相談して決めると安心です。
Q2.危篤状態が回復することはありますか?
医師から危篤と診断された場合でも、必ずしもすぐに死を迎えるとは限りません。病状や体力、医療処置によっては一時的に持ち直すケースもあります。
ただし、危篤は基本的に回復の可能性が低いとされる状態です。そのため、ご家族は「悔いのないように寄り添う時間を持つこと」を大切にすると良いでしょう。
Q3.危篤に備えてできる準備はありますか?
自分自身やご家族に万が一が起きたときに備えることは、大切な終活の一つです。そのため、以下のような準備をしておくと安心です。
- 延命治療に関する希望を明確にする(リビング・ウィル=事前指示書の作成など)
- エンディングノートの作成
- 保険証・通帳・印鑑・年金証書・財産関連書類などの整理
- 葬儀社の情報収集や事前相談
こうした準備や本人の意思を家族間で共有しておくことで、いざという時も冷静に対応でき、安心につながります。
おわりに
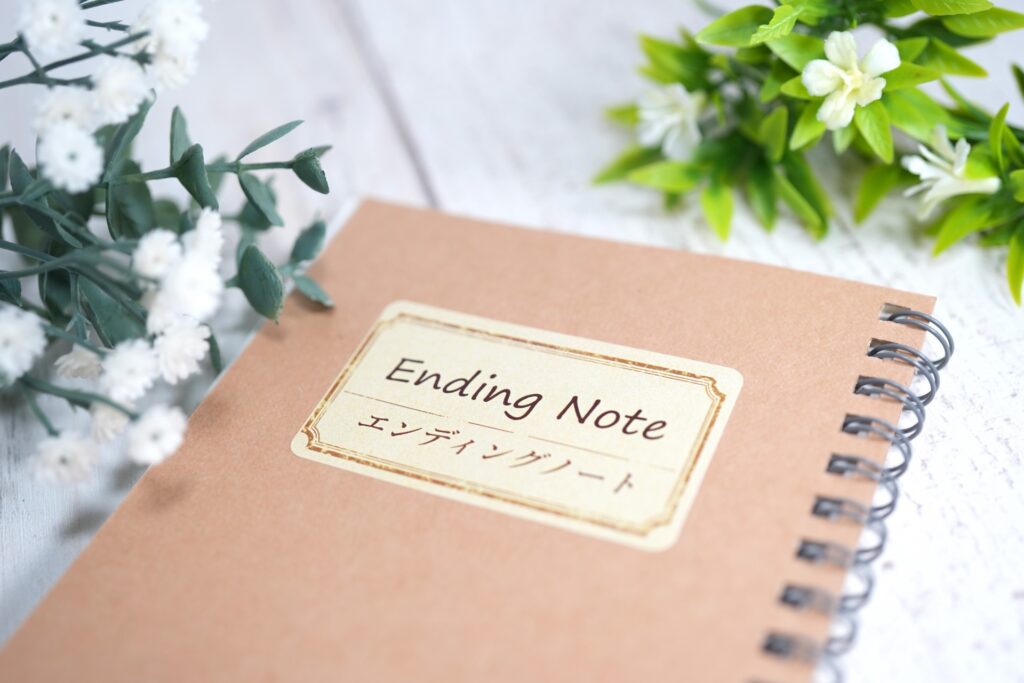
危篤の状態だと診断されると、ご家族が動揺してしまうのは当然のことです。しかし、ご本人と一緒に過ごせる限られた最後の時間でもあるため、できる限り悔いが残らないように過ごしたいものです。
医療現場では容体の急変も珍しくありません。そのため、いざという時に慌てることなく対応できるよう、事前に基本的な知識を持っておくことで、心の準備にもつながります。
この記事では、「危篤とはどういう状態か」から「誰に連絡するか」「対応の流れ」「万が一の場合の行動」までを網羅的にご紹介しました。
最期の時間を悔いなく過ごすためにも、この記事が参考になれば幸いです。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
