初盆(はつぼん)とは、故人様が亡くなられてから初めて迎えるお盆のことです。故人様の精霊(しょうりょう)がはじめて家に戻られる初盆は、特別な意味を持つ仏教行事のため、より丁寧な準備と心のこもったおもてなしが大切になります。
しかしながら、普段のお盆とどのような違いがあるのか、どういった準備が必要になるのかなど分からないことも多いため、不安を感じる方も多いようです。
そこで本記事では、初盆の意味や通常のお盆との違い、必要な準備、当日の流れ、適切な服装やマナーについて、わかりやすく解説いたします。
初盆を迎えるご家族の方に安心して準備をお進めいただけるよう、実用的なチェックリストとともにご紹介いたします。
初盆(新盆)とは?通常のお盆との違いについて

初盆(はつぼん)とは、故人様が亡くなられてから初めて迎えるお盆のことを指します。まず、初盆とは何か、そして通常のお盆とはどのような点で異なるのかについて、詳しくご説明いたします。
初盆と新盆の違いは?
故人様が亡くなられてから初めて迎えるお盆を「初盆(はつぼん)」と呼びますが、地域によっては「新盆(にいぼん・しんぼん)」という呼び方をする場合もあります。
呼び方は異なりますが、いずれも同じ意味を表しており、内容に違いはありません。
どちらも、四十九日の忌明け後に初めて迎えるお盆のことで、通常のお盆よりも手厚く丁寧に供養を行うという特徴があります。
通常のお盆との違い
通常のお盆は、毎年8月(地域によっては7月)に、ご先祖様の霊をお迎えして供養する年中行事です。お盆行事は、仏教の「盂蘭盆会(うらぼんえ)」を起源とし、7世紀頃に中国から日本に伝来したとされています。
その後、日本古来の祖霊信仰と融合し、日本独自の先祖供養の風習・伝統行事として発展を遂げました。
初盆は、このようなお盆の中でも特別な意味を持つ重要な行事です。故人様が仏様となられ、初めてご自宅にお帰りになるとされる大切な機会であり、ご家族や親族が心を一つにしてお迎えいたします。
白提灯(白紋天)を飾り、僧侶をお招きして法要を営むなど、通常のお盆以上に手厚い供養を行うのが一般的です。
初盆はいつ?2025年の日程をチェック

初盆と通常のお盆の違いについてご説明いたしました。続いて、初盆をいつ行うのか、四十九日法要との関係や2025年の具体的な日程について解説いたします。
初盆を行う年の数え方
初盆は、故人様の四十九日法要を終えられた後に初めて迎えるお盆の時期に行います。つまり、四十九日法要よりも前にお盆の期間が到来する場合は、その年ではなく翌年のお盆が初盆となります。
【2025年版】初盆はいつ?
2025年のお盆は、8月13日(迎え盆)〜8月16日(送り盆)が一般的ですが、地域や宗派によって時期が異なる場合があります。
関東の一部地域などでは7月に行われる一方、沖縄・奄美地域などでは9月4日〜6日に行われるなど、お盆の時期には地域差が見られます。
また、初盆においては、関西地方の一部地域で「七日盆」と呼ばれる風習があり、8月7日に故人様の魂をお迎えし、より長い期間をかけて丁寧に供養するという慣習が残っている地域もあります。
お住まいの地域の慣習について、事前に確認されることをおすすめします。
初盆が翌年となるケースとは?
初盆は、四十九日法要後に最初に迎えるお盆に行うものです。故人様がお亡くなりになってから日が浅く、四十九日法要前にお盆の期間が到来する場合は、翌年のお盆時期に初盆供養を執り行うのが一般的な慣例となっています。
初盆の準備|チェックリストで確認しよう

初盆を迎えるにあたり、何を準備すればよいのかをリスト形式でご紹介します。忘れ物の防止にお役立てください。
法要の準備
- 僧侶の手配
菩提寺がある場合は、早めにお寺と連絡を取り、法要の日程を相談しましょう。 - 会場・日時の決定
自宅や菩提寺で行う場合もあれば、斎場や会館を借りることもあります。家族の都合も考慮して決めましょう。 - 参列者への案内
親族やごく親しい知人に日時や場所を早めに案内しましょう。案内状を送るとより丁寧な印象です。 - お布施の用意
僧侶へのお礼として「お布施」を準備しましょう。金額は地域や菩提寺によって異なるため、事前に確認されることをおすすめします。 - 会食(お斎)の手配
法要後に会食を行う場合は、仕出しや会食場所を予約しましょう。 - お返し(返礼品)の準備
参列者への感謝として、タオルやお菓子などの返礼品を用意するのが一般的です。
飾りの準備
- 白提灯(白紋天)の設置
故人様の霊が迷うことなく帰ってこられるよう、目標となる白提灯(白紋天)を玄関先や仏壇のそばに飾りましょう。 - 精霊棚(盆棚)の設置
仏壇の前に故人様の霊が滞在するための棚を設けます。盆花や果物、故人様の好物などをお供えしましょう。 - 供物(花、果物、菓子など)の用意
仏壇に季節の果物やお菓子、線香などをお供えしましょう。華やかで清らかな飾りのものが好まれます。
初盆当日の流れと過ごし方

準備と併せて、初盆当日をどのように過ごすかについても詳しくご説明いたします。迎え盆から送り盆まで、日ごとの流れを順を追ってご紹介いたします。
13日:迎え盆
- お墓掃除とお墓参り
お墓をきれいに整え、故人様の霊をお迎えします。 - 迎え火を焚く
故人様の霊を自宅にお迎えするための目印として、玄関先などで「おがら」を焚きます。 - 白提灯や盆提灯に火を灯す
故人様の霊が迷わずにご帰宅されるよう、提灯に火を灯して導きます。
14〜15日:法要・供養の中心日
- 僧侶による読経・法要
家族や親族が集まり、僧侶の読経のもと、故人様のご冥福をお祈りします。 - 参列者とともに会食
法要後に会食の席を設け、故人様の思い出などを語りながら心をひとつにする時間を持ちます。
16日:送り盆
- 送り火を焚いて故人を見送る
再び「おがら」を焚き、故人様の霊が迷わずにあの世へ戻れるようお見送りします。 - 飾りや供物の片付け
精霊棚や供物、白提灯などを片付けます。なお白提灯は、初盆でのみ使用する盆提灯ですので、通常はお焚き上げなどで処分するのが一般的です
初盆の服装とマナー|遺族・参列者別に解説
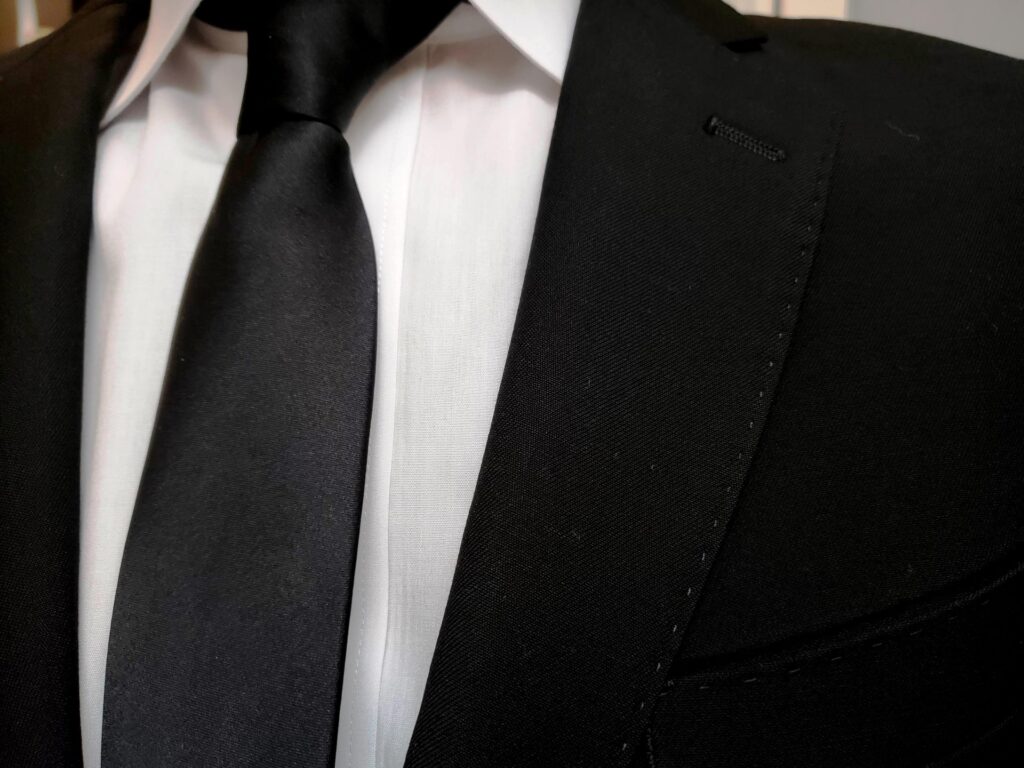
初盆当日の過ごし方についてご説明いたしましたが、服装やマナーについて気になる方も多いのではないでしょうか。ここからは、遺族・参列者それぞれが心がけたい身だしなみと振る舞いについて確認してまいりましょう。
遺族・親族の服装
遺族や親族は、喪服(黒の礼服)を着用するのが基本です。女性は黒のワンピースやスーツ、男性はブラックスーツが一般的です。
参列者の服装
参列者の場合は、派手な色味やデザインのものでなければブラックフォーマルでなくても問題ないという意見もありますが、遺族・親族と同様、喪服(黒の礼服)の着用が賢明です。
子ども・学生の服装
学生の方は制服が正式な装いとなります。制服をお持ちでない小さなお子様には、白や紺、グレーなど落ち着いた色合いの服装をお選びください。
※お子さまの服装マナーについては『【板橋区・荒川区のご葬儀】子どもがお葬式に参列するときの服装|年齢別マナーと季節ごとの注意点も解説』で詳しくご紹介しております。
初盆での挨拶やふるまいの基本
「この度は初盆を迎えられまして…」といった言葉で、丁寧にお悔やみとお見舞いの気持ちをお伝えするとよろしいでしょう。お香典をお渡しする際にも、一言添えていただくとより丁寧な印象となります。
よくあるご質問|初盆にまつわる疑問を解決
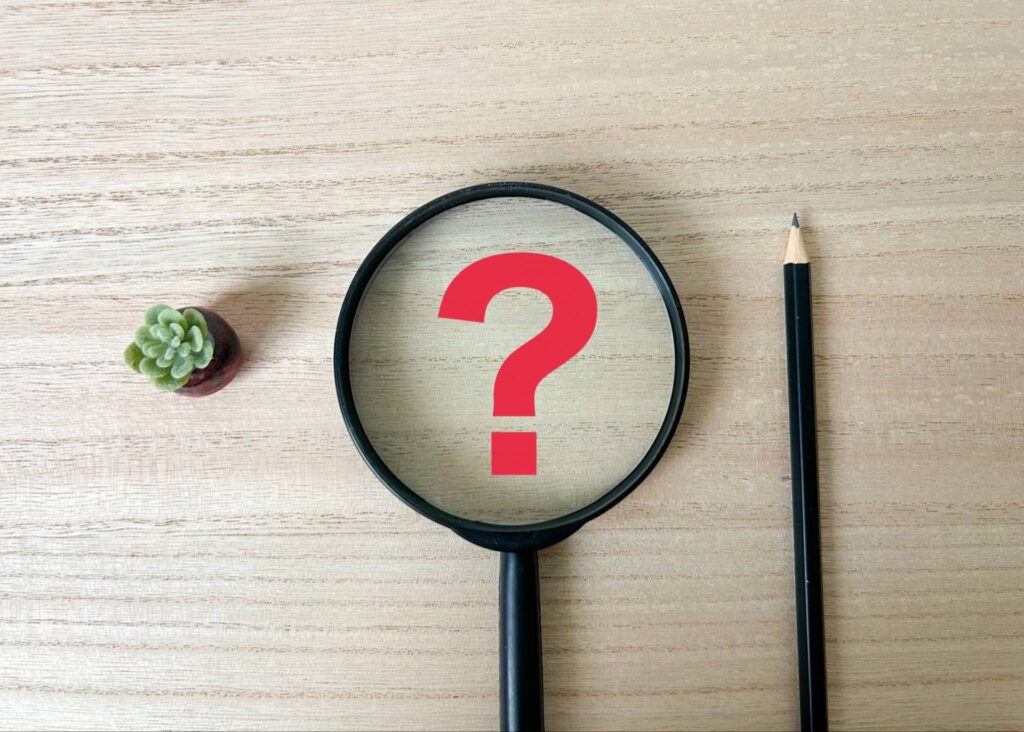
初盆の準備や当日の流れについてご理解いただけたとしても、費用面や後片付け、心構えなど、細かな疑問は尽きないものです。ここでは、特によくいただく3つのご質問にお答えいたします。
Q1. 初盆にはどれくらいの費用がかかりますか?
A. 法要・会食・返礼品などを含めて、数万円〜十数万円が目安です。
初盆にかかる費用は、法要や僧侶へのお布施、会食(お斎)、返礼品(引き物)の内容によって異なりますが、数万円から十数万円程度が一般的な相場とされております。なお、規模や地域の慣習、どの程度丁寧に行うかによっても大きく変わってまいります。
- 僧侶へのお布施:2〜5万円程度
- 会食費:1人あたり3,000〜5,000円程度
- 返礼品:1人あたり1,000〜3,000円程度
また、参列者が持参する香典の相場は以下の通りです。
- 親族・親しい間柄:5,000〜10,000円
- 友人・知人:3,000〜5,000円
- 会社関係:3,000円前後
香典袋には「御仏前」や「御供」など、宗派に応じた表書きとしましょう。
Q2. 初盆が終わったら飾りや道具はどうすればいいですか?
A. 白提灯はお焚き上げやお清めで処分し、他の飾りは清潔に保管を。
初盆で使用した白提灯(白紋天)は、故人様の霊を初めてお迎えするためだけの特別な提灯です。ご使用後は、お寺でのお焚き上げや、塩やお酒でお清めしてからご処分いただくのが一般的です。
その他の道具(精霊棚、通常の盆提灯など)は来年以降もお使いいただけるため、以下の手順で丁寧に保管いたしましょう。
- 丁寧にほこりを払う
- しっかり乾燥させる
- 箱や収納袋に入れる
といった形で保管するようにしましょう。
※ビニール袋などに入れたまま保管されますと、カビや変色の原因となる場合がございますのでご注意ください。
Q3. 初盆を迎えるにあたって、どんな気持ちで臨めばよいですか?
A. 形式よりも、故人への想いを大切にする気持ちが何よりです。
初盆は単なる儀式ではなく、ご家族で故人様を偲び、在りし日のお姿に思いを馳せる大切な時間です。形式にとらわれ過ぎることなく、心を込めて丁寧に供養されることが最も重要です。
また、小さなお子様や若い世代の方と一緒に過ごす初盆は、命のつながりやご家族の歴史をお伝えする貴重な機会でもあります。
日々の忙しさの中でも、少し立ち止まって、ご家族との時間を大切にしていただければと思います。
おわりに

初盆は、故人様を初めてお迎えし、手厚くご供養する大切な行事です。準備やマナーなど、慣れないことも多く不安を感じられるかもしれませんが、何より大切なのは故人様を想う気持ちです。
ご家族や親族の皆様が心を寄せ合い、在りし日のお姿を思い出しながら過ごされる時間は、きっと忘れがたいものとなることでしょう。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
