葬儀の日取りを決める際、「友引の日は避けた方がよい」という話を耳にしたことはありませんか?この慣習は、六曜(ろくよう)と呼ばれる暦注の一つに由来するものです。
六曜は「その日の吉凶」を表すとされており、友引もその中の一つとして位置づけられています。しかし実際には、さまざまな事情から、友引の日に葬儀を執り行うケースも少なくありません。
そこで本記事では、友引の日に葬儀を行っても問題ないのか、なぜ避けるべきと言われるのか、そして友引を含む六曜の意味について詳しく解説します。
また、日柄以外に葬儀の日程を決める際に考慮すべき要素についてもご紹介しますので、葬儀の日取りを決める際の参考としてお役立てください。
結論:友引の葬儀は問題ない

まずは結論からお伝えいたします。
友引の日に葬儀を執り行うこと自体は、宗教的な観点から見ても全く問題ありません。実際のところ、友引であっても火葬場が稼働している地域では、友引の日に葬儀を執り行うこと自体は可能です。
しかし一方で、「友引の葬儀は避けるべき」という通説が根強く残っていることも事実です。この日柄に葬儀を行うことに対して、疑問を感じる方も少なくないでしょう。
なぜこのような考え方が広まったのか、そして実際のところ友引の葬儀は本当に問題ないのか、ここから詳しく掘り下げていきます。
「友引の葬儀は縁起が悪い」は迷信
古くから伝わる言い伝えとして、「友引の日の葬儀は避けるべき」というものがあります。これは、六曜の「友引」に「凶事に友を道連れにする」という意味があるとされ、「友引の日の葬儀=縁起が悪い」と解釈されてきたことに由来します。
しかし、友引は元来「共引」と表記されており、「勝負がつかない日」「引き分けの日」という意味でした。この本来の意味を考えると、葬儀を避ける理由は見当たりません。
いずれにしても、これらの考え方に科学的な根拠はなく、あくまで迷信の一つに過ぎないのが実情です。
とはいえ、伝統的な考え方を重んじる方が多いことも確かですので、周囲への配慮は必要でしょう。
全国的に「友引」の日を火葬場の休業日に充てている地域は多いものの、稼働している地域(関西地域など)も少なからず存在します。
こうした地域では、友引であっても葬儀を執り行うことは可能ですが、故人様の魂が寂しくないように、副葬品として「友人形(友引人形)」を棺に納める習慣が残されています。
こうした習わしも、縁起の良し悪しを気に掛ける方への配慮の1つといえるでしょう。
宗教的に問題はない
前述の通り、友引の日の葬儀は宗教上の観点からは何の問題もありません。主要な宗教ごとに詳しく解説いたします。
仏教
「仏滅」という六曜があるため、六曜が仏教に由来しているように感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は両者の間には全く関係性がありません。
六曜は中国から伝わった占いが元であり、仏教の教義にはこのような考え方は存在しません。そのため、仏教では、友引だけでなく、どの日柄の日であっても葬儀を執り行うことに問題はないとされています。
神式
神道においても、六曜は重視されていません。神道では死を「穢れ(けがれ)」として捉えるため、葬儀に関して独自の作法や配慮が求められますが、日柄を理由に葬儀を避けるという教えはありません。そのため、友引であっても問題なく葬儀を執り行うことができます。
キリスト教
キリスト教には、そもそも特定の「日柄」を気にする習慣はありません。キリスト教における葬儀は、神への祈りと故人様を偲ぶための大切な儀式であり、友引であるかどうかに関わらず、日柄による縁起を気にする必要はないとされています。
友引を含む六曜の意味

友引に葬儀を予定しても問題ないことについて解説しましたが、ここで、“そもそも六曜とは何か”についてもご紹介します。
六曜とは、暦に記載される日時・方位などの吉凶、その日の運勢などを表す暦注(れきちゅう)のひとつとされ、その日の善し悪し(日柄)を表しています。
一般のカレンダーや手帳などに記載されていることも少なくなく、先勝、友引、先負、仏滅、大安、赤口の順に繰り返し記されています。それぞれに次のような意味があると言われています。
先勝(せんしょう/せんかち)
「先んずれば即ち勝つ」という意味で、午前中が吉、午後は凶とされます。何事も急いで行うのが良い日です。
友引(ともびき)
元々は「共引」と書き、勝負事で決着がつかず引き分けになる日という意味でした。しかし、後に「友を引く」という字が当てられ、「凶事(葬儀など)を行うと友を道連れにする」という迷信が生まれました。
一方で、慶事(お祝い事)においては「幸せをお裾分けする」として吉とされます。正午のみ凶、それ以外は吉とされています。
先負(せんぷ/せんまけ)
「先んずれば即ち負ける」という意味で、午前中は凶、午後は吉とされます。何事も急がず、平静を保つのが良い日です。勝負事や急用は避けるべきとされています。
仏滅(ぶつめつ)
六曜の中で最も凶の日とされ、「物滅」として「物事が一旦滅び、新たに始まる」という意味合いもあります。そのため、何かを始めるには、むしろ良い日とする解釈もあります。
ただし、「仏事(法事やお葬式)」とは無関係であり、仏教上の根拠はありません。
大安(たいあん)
「大いに安し」という意味で、万事において吉とされる最良の日です。特に慶事に最適とされています。
赤口(しゃっこう/しゃっく)
正午のみが吉で、それ以外の時間帯は凶とされます。「赤」の字から、火の元や刃物など、死や争いを連想させるものに注意が必要な日と言われています。
友引の日に葬儀が避けられる理由

六曜の意味をご理解いただいたところで、友引の日に葬儀が避けられがちな具体的な理由について詳しくご紹介いたします。
六曜を重んじる習慣が根強いため
故人様はもちろんのこと、葬儀に参列される方の中には、六曜の考え方を大切にされる方が多くいらっしゃいます。特にご年配の方々を中心に、友引の日に葬儀を執り行うことに対して、抵抗感や疑問を抱くケースは少なくありません。
葬儀は故人様を偲び、ご遺族様や参列者の皆様が心安らかにお別れをするための大切な儀式です。すべての方に安心してご参列いただくためにも、周囲の心情に配慮した日程調整は重要な検討事項の一つといえるでしょう。
火葬場の休業日と重なるため
友引の日の葬儀が敬遠される慣習を受けて、全国の多くの火葬場では友引を定休日としています。これは需要の少なさと、施設運営の効率化を図るためです。
火葬場が休業していれば、当然ながら葬儀を執り行うことはできませんので、火葬場の営業日に合わせて通夜・葬儀の日程を決定する必要があります。
そのため、葬儀の日程を検討する際は、まず火葬場の営業日や空き状況を確認することが不可欠です。
葬儀の日程を決める際に配慮すべきこと

友引に葬儀が敬遠される理由についてご紹介しましたが、葬儀の日取りは六曜などの日柄だけで決定するものではありません。
大切なのは、さまざまな状況を総合的に考慮し、ご遺族様にとって無理のないかたちで日程を整えることです。
ここからは、葬儀の日程を決定する際に配慮すべき重要な事項について詳しくご説明いたします。
法的手続きと火葬許可証の取得
葬儀を執り行う前に、法律に基づいた手続きを完了させる必要があります。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
火葬を行うためには、以下の手続きが必要です。
- 死亡届の提出先:故人様の死亡地・本籍地、または届出人の住所地の市区町村役場
- 火葬許可証の交付:死亡届提出時に市区町村長から交付を受ける
- 提出期限:死亡の事実を知った日から7日以内
※根拠法令:墓地、埋葬等に関する法律第5条、第8条
休業日の対応について
土・日・祝日や年末年始など、市区町村役場の休業日に手続きが必要な場合は、休日窓口の開設状況や取扱業務などを確認したうえで、適切に対処しましょう。
※多くの自治体では、休日でも死亡届の受付を行う体制を整えています。また葬儀社の多くでは、こうした地域の行政手続きに関する情報もきちんと把握していますので、遠慮なく相談されることをおすすめします。
参列者が集まりやすい日程の設定
葬儀は故人様を偲び、心を込めてお別れをする大切な場です。ご遺族様だけでなく、ご親族、ご友人、故人とご縁のあった方々が無理なく参列できるよう、日程には十分な配慮が求められます。
特に遠方から訪れる方やご高齢の方がいる場合は、移動に負担がかからないよう、余裕のあるスケジュールを心がけると安心です。
火葬場の予約状況の確認
現実的な日程決定において、火葬場の空き状況は最も重要な要素の一つです。
予約の取りにくい時期
- 年末年始:12月29日〜1月3日頃
- お盆期間:8月13日〜16日頃
- 大型連休:ゴールデンウィークなど
- 友引明け:友引の翌日は予約が集中しやすい
都市部特有の課題
人口密度の高い都市部では、火葬場の需要が高く、希望する日時に予約が取れない場合があります。特に東京都心部などでは、数日から一週間程度待つこともあります。
確認すべきポイント
- 火葬場の営業日(友引の休業日を含む)
- 希望日時の空き状況
- 火葬時間と所要時間
- 料金体系(市民・市外料金の違いなど
これらの要素を総合的に検討し、故人様とご遺族様にとって最も適した日程を決定することが、心に残る葬儀の第一歩となります。
※多くの葬儀社では、火葬場の予約状況に応じて、最適な日程を提案してくれますので、過度に心配する必要はありません。
友引の葬儀に関してよくある質問
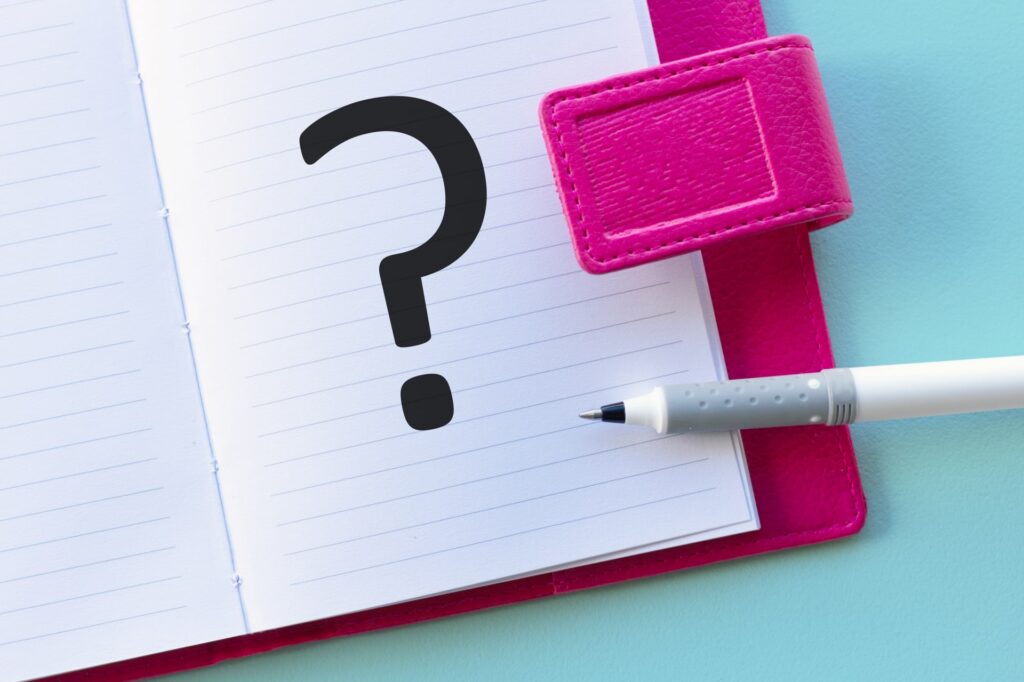
友引に関する葬儀の実施について、皆さまからよく寄せられるご質問とその回答をまとめました。
Q1:友引に葬儀をすると本当に友人を道連れにしてしまうのでしょうか?
A1:いいえ、それは単なる迷信に過ぎません。友引の日に葬儀を行ったからといって、友人が不幸になる、あるいは「道連れになる」といった科学的な根拠は一切ありません。現代では、このような迷信を気にしない方も増えてきています。
しかし、一方で依然として六曜や日柄を重んじる方も多くいらっしゃいます。もし友引の日に葬儀を執り行う場合は、参列される方々のお気持ちにも配慮し、必要に応じて事前に説明をするなどの対応を検討すると良いでしょう。
Q2:火葬場が友引の日を休業とするのはなぜですか?
A2:火葬場が友引の日を休業とする主な理由は、「友引の日の葬儀は縁起が悪い」という日本の慣習や迷信に配慮しているためです。くわえて、葬儀の需要自体が少ないと見込まれるため、効率的な運営を図る意味合いもあります。
ただし、この扱いは全国一律ではありません。地域や施設によっては、友引でも火葬を受け付けている場合があります。
Q3:友引に葬儀をする場合、何か特別な配慮が必要ですか?
A3:友引の日の葬儀は、宗教的な観点からは何ら問題ありません。しかし、前述の通り、参列者の中には日柄を気にする方もいらっしゃる可能性があります。
そのため、もし友引の日に葬儀を行う場合は、参列者の皆さまが安心して故人様をお見送りできるよう、配慮の気持ちを示すことが大切です。
例えば、葬儀の日程を決めた理由(火葬場の空き状況やご家族の都合など)を説明したり、事前に理解を求めるメッセージを伝えたりするなどの工夫が考えられます。
これにより、参列者の方々も納得し、心穏やかに葬儀に参列できるでしょう。
おわりに
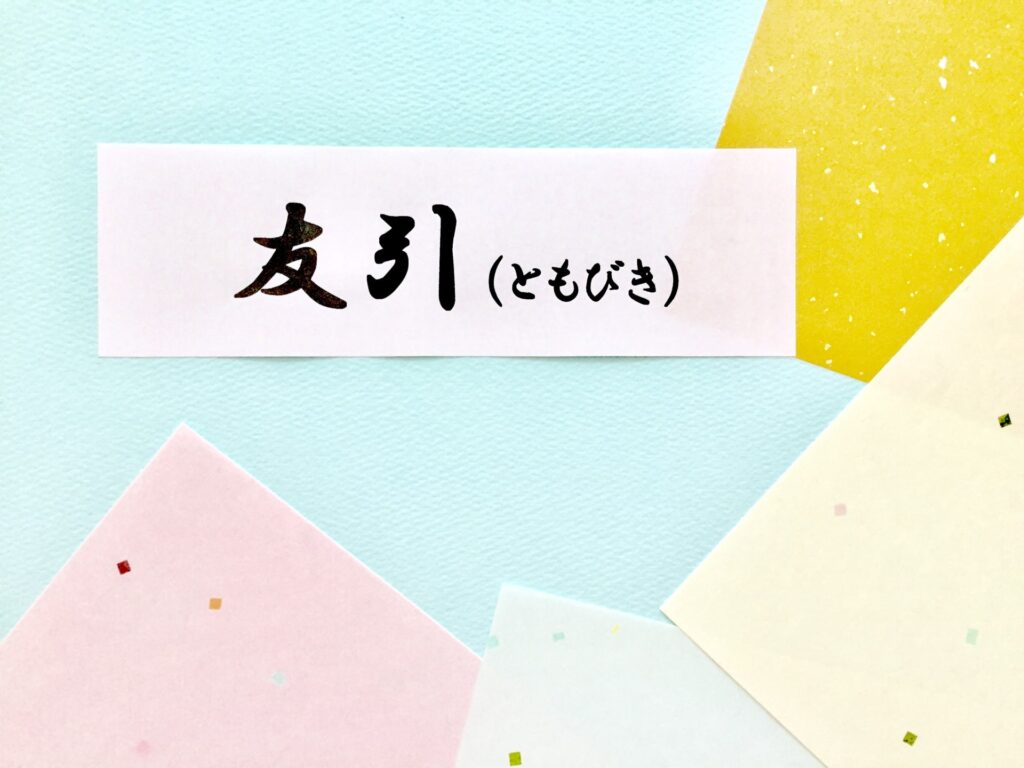
今回は、友引の日に葬儀を避けるという慣習について詳しく解説してきました。宗教的な観点から見れば、友引に葬儀を執り行うことは何ら問題ありません。しかし、六曜という日柄を重視される方が多くいらっしゃる点や、それに伴って多くの火葬場が友引を休業日としているという現実的な問題があることもご理解いただけたかと思います。
最も大切なことは、日柄に縛られることではなく、ご遺族や参列者の皆さまが故人様を心ゆくまで悼み、感謝の気持ちを込めてお見送りできる葬儀であることです。そのためには、六曜の意味を理解しつつも、参列者の心情への配慮、火葬場の空き状況、そして何よりも故人様やご家族の意向を総合的に考慮して、最適な日取りを選択することが重要です。
板橋区・荒川区の《家族葬専門 自由なお葬式》では、ご葬儀に関する疑問や不安を解消いただけるよう、LINE公式アカウントを開設いたしました。
友だち登録するだけで、気軽にご相談いただけますので、ぜひご利用ください。
 03-6806-7440
03-6806-7440 
 お急ぎの方へ
お急ぎの方へ
